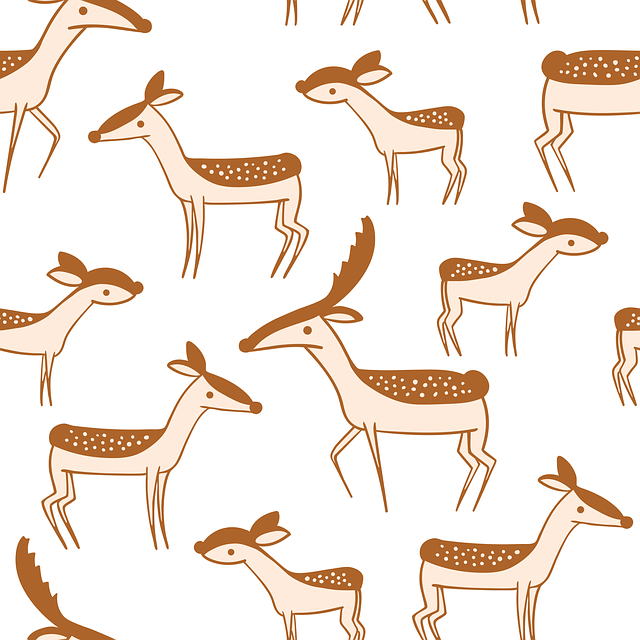1.1
「ようこそいらした。無理の国からとは珍しい。このハルの里から行くものはいても、里に帰るものは少ない。ましてや生まれが無理の国の人など。」
朝になり、ナチュボたちが会いたいと言っていると、里の中央にある建屋に案内された。
「暖かく迎えていただいて感謝しています。皆さま何とお呼びすれば」
奇妙なことに、4人とも全く同じ外見をしている。よく見ると羊織の羽織の模様が違う。
「我々は生まれたころよりナチュボであり、そしてナチュボは我々一人ひとりでもあり、同時に我々総体でもある」
何を言っているのかわからないが、しかしそれはおれが理の国に疎いからだろうか。
「それは、ハルの里の理と何か。私は理の国の、各里に伝わる理を見聞しようと、無理の国から来たのです」
「なんと、しかしそれは無理の国の人だからできること」
どういうことか分からず返答につまる。場に静寂が満ちると、右端のナチュボが語をつないだ。
「理の国では、それぞれが理を持つがゆえに、他の方の理を覗き見るようなことをすれば理と理が相対する」
そのナチュボの羽織には、燃え盛る炎のようなモチーフがあしらわれていた。
「無理の国の人であれば、かえってこの先理の国で自由になる。かならずしも歓迎されぬかもしれぬが」
炎のナチュボの隣のナチュボが、目を据えてゆっくりと、しかしわずかに微笑みながら語り掛けてきた。
「理というものを一つも知らないのです。理の一端を知りたい、この里の理を教えていただけませんか」
「我々も一つしかしらない。知る理が多ければ良いというものでもない。無理というのはまた特殊だがね。ハルの里の理は極めて単純なのだ。」
初めに挨拶を述べたナチュボが、立ち上がり言う。