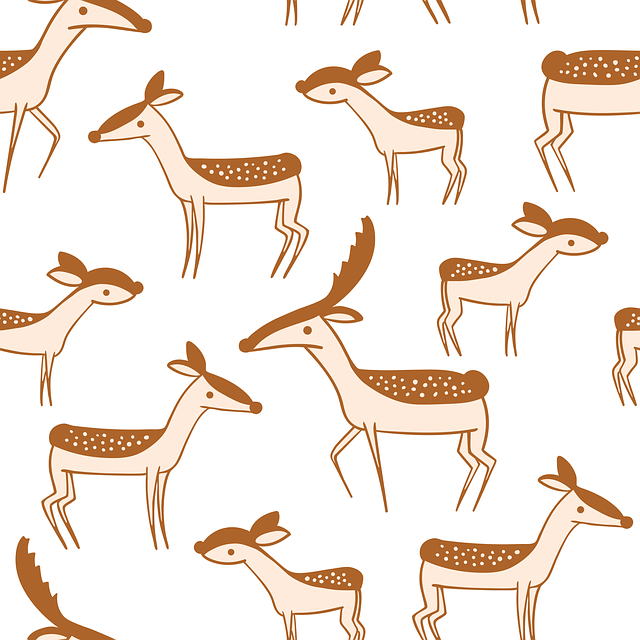一人では何もできない人間が、何人集まったところで、何もできない集団しか形成されない。そうした集団は、やがて同調圧力を強めていく。ともに無力であることへの安堵に浸り、個の輪郭が薄れていく。そうして、最後にはただの風景の一部となり、生を終える。そうはなりたくないと皆がもがく。
人や集団が何かを「成す」とは、一体どういうことなのか。どの時点で、「何かを成した」と言えるのか。その価値は、誰が決めるのか。
もし価値判断を外部に委ねるのならば、それは結局、”風景”に根拠を求めることになる。世間が評価するものだけが価値を持つとするならば、その価値に自分の手触りはない。ただ、その場に佇み、誰かが決めた「価値」に背を預けることしかできない。いずれその虚しさに気づく。
かといって、価値の根源を自らの内に求めたとして、それはどこまで確かだろうか。盲信によって支えられた価値観は、やがて自他の対立を深める。認められることへの渇望を生み、世に受け入れられないことへの焦燥を募らせるだけではないか。
風景となることを拒みながら、風景に溶け込むことを求める。私は一人では何もできない。