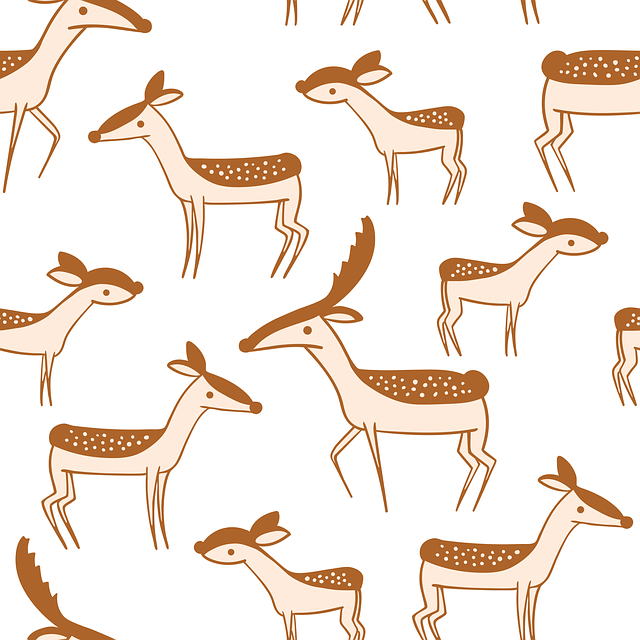0.0
逃げ出すように歩いてきた。
「理の国へ、来た」
1.0
あらゆる理は無価値である、という無理の国に浸透した思想に耐えきれなくなり、西の国境を目指したのは3ヶ月前のことだった。互いに無干渉を貫く理の国との国境は、理の国からの「布理者」の通行が制限されるのみだが、麓へ降りてくるまでにすれ違ったのは小規模の行商隊だけであった。
理の国には、集落ごとに特有の理を信望する文化がある。そう伝え聞いたのは200の月を少し超えた頃だったか。250の月を超えれば「無理の人」として名簿に名が加わる。職が割り振られる前のこの最後の期間に、名も知れぬ理の国の集落を見て回るのだ。
「理の国へ行くのか。却って空虚にならんとせんでも良いのに」
父の言葉を振り切るように、おれは歩みを進めてきた。
100ほどの小屋が点在する牧草地の中に、赤い札を掲げる小綺麗な建屋が見える。地の寒さから逃れられるだけでも随分ましな夜となるだろう。
「一晩泊めていただけないか。無理の国から来た」
「へえ、無理の国から。ハルの里でも久しぶりだよ。ここに名前を、いや無理の人ならもう脱名してるか」
120の月かと思われる男児の様子から、ここが国境付近であることが思い出される。
「脱名はまだだ、ベインという」
「まあなんでもいいんだ。無理の国の人の時にはナチュボたちの許可がいるんだ。ちょっと待ってて」
「ナチュボ?」
不可解な響きに問い直してしまう。聞くところによる理の国の理の一端であろうか。
「うちの里の偉い人たちのことだよ、村の資金を使って行商人からものを買う4人がいるんだ」
「売らないのか」
「あっはっは、面白いこというんだね。そんなことするのは里のはずれの炭鉱奴隷だけだよ。はなしはまたあとでね」
羊肉のもてなし、豪奢とはいえないが清潔な寝床にも関わらず、代金はとらないという。長旅になるであろう理の国での初日としては悪くないが、一抹の違和感を抱えながら床に就いた。